日本の食料自給「力」の向上と農地の維持には、市場創造が不可欠だ!
はじめに
ロシアのウクライナ軍事侵攻は、世界に大きな衝撃を与えた。事態の長期化を受けて、安全保障についての意識も高まっている。このような中、EU、特にドイツを中心にロシアからの天然ガス輸入などがクローズアップされることは多いが、ウクライナとロシアは以前から小麦の輸出大国であることも改めて認識された。エネルギーのみならず食料についても、今後世界中に大きな波紋を起こしていくことが推測される。
日本国内においても、従来から食料自給率の問題は安全保障の観点から議論されてきた。しかし、少子高齢化、人口減少社会の時代にあっても、食料自給率は一貫して減少している。生産量が減り続けているからである。
とは言え、社会全体としての危機感は強くない。それは次のような理由によるのではないか。1980年代から、日米の貿易摩擦や円高の影響もあって急速に海外への直接投資を行うようになった日本の製造業は、効率的なグローバル生産体制とサプライチェーンを構築することで乗り切ってきた。そして、情報技術の革新や自由貿易主義の浸透などを信奉する日本人の多くは、自国で消費する食料についてもグローバル調達が世界のスタンダードであると考えている。しかし、この考えはロシアの侵攻によって、一夜にして変わった。これまで熱心に議論されてこなかった様々な課題について、今後はより本質的な議論が起きてくることだろう。
そこで今回は、安全保障の観点から日本の食料自給率の問題を考える糸口として、ベトナムで栽培されている“長粒米”を日本の農地で栽培し、6次産業化によるビジネスモデルを展開する「株式会社ペントフォーク」の伊藤武範社長に話を聞いた。

《PROFILE》
伊藤 武範
Takenori Ito
1975年、石川県生まれ。金沢大学を卒業後、NTTコムウェアに就職。2008年NTTコミュニケーションズに転職し、ベトナムへ。2013年帰国、その後外資系での営業部長を経て、福井県に移住。2015年、アジチファーム(現・株式会社ペントフォーク)に参画する。
日本の農政を取り巻く環境変化とは
―日本の農政を取り巻く環境の変化から教えてください。
米の政策をめぐっては、時代の流れの中で何度か大きな修正が行われました。1962年をピークに、一人当たりの米消費量は減少の一途を辿っています。具体的には1962年に118キロの米を消費していたものが、2010年には53.5キロにまで減ってしまった[1]。1960年代に1400万トンを超えていた生産量も、近年では主食米の生産量は700万トン程度であり、需要量は毎年約10万トンずつ減っています。
2013年に決定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」は、2018年を目途にこれまで行政が行ってきた生産数量目標の配分に頼らず、需要に応じた生産が行われるよう、次の2つの方針が示された点で画期的でした。まず1つ目は、行政の生産調整をやめることであり、2つ目が米の直接支払交付金を廃止することです[2]。
[1] https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyukyu/index.html
[2] https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_seisaku_kaikaku.html

―大きな変更ですね。保護貿易より自由貿易が日本社会にとってより良い結果をもたらすだろうという漠然とした理解があった中で、グローバルな環境変化に対応せず、従来と同じことを繰り返すことをよしとしてきた農業政策が、日本社会全体として共感を得られなくなった。
2018年に発効したTPP(環太平洋パートナーシップ)のことを覚えている人も多いと思うのですが、農業保護の観点から日本農業については防戦一方という印象は拭えません。このような環境変化の中で、日本の米政策も修正を余儀なくされたんですね。
米の需要の減少が、米の生産量の減少を求め、当然減反政策の思想に繋がっています。しかし、このような発想は、農業従事者の高齢化や減少、さらに耕作放棄と相まって、日本の農地の消滅という形で新たな問題を提起することになりました。2021年における農業従事者の平均年齢は67.9歳であり、2015年に175万人だった農業従事者は、2021年には130万人にまで減少しています。
一旦放棄され荒れた農地は簡単には元に戻らず、過疎化が進む現場は消滅の危機を迎えているのです。そこで、「農林水産業・地域の活力創造プラン」が策定され、環境変化への対応を促す取り組みにより、水田のフル活用が政策目標になりました。具体的には、食料米から、麦、大豆、飼料用米などへの転換が意図されました。
ベトナムの“長粒米”を、福井で育てる
―未来の日本農業が模索される中、今後はおそらく国家の安全保障という観点がクローズアップされることになるでしょうね。近年、食料自給率と並んで食料自給力という言葉をよく目にします。食料自給力とは、日本の農林水産業の潜在的な生産能力をフル活用した場合に得られると期待される食糧の供給可能熱量の試算です。例えば、花などの非食用作物をイモ類に変更したり、耕作放棄地を使用したりした場合にどうなるかを試算している。このような極端なケースを想定しないと安全保障の議論ができなくなっている。しかし、食料自給力の課題を解決するには、従来の常識を超えた農地のフル活用に知恵を絞る方が重要です。
伊藤社長が取り組まれている福井県でベトナムの長粒米を育てるというアイデアは、ある意味、非常識な新しい知恵です。どうしてこのようなアクティブなアイデアに辿り着いたのですか?
2008年、ベトナムの外資規制が外れたタイミングを契機に、NTTコミュニケーションズ側が20億円を出資し、ベトナム側のVNBTが20億円を出資する形で、ベトナム国内にデータセンターの企業を設立することになりました。仮にNTTコミュニケーションズが出資した20億円を使い切ったとしても、責任は問われないという魅力あふれるプロジェクトでした(笑)。すでに勤めていたのですが、このグループ内の転職制度に手を挙げて、ベトナムの首都・ハノイで5年間勤務しました。日本人が私を含めて2人とベトナム人5人という職場でしたが、ここでの経験がベトナムとのつながりの始まりです。
ハノイで暮らすようになって、ベトナム料理のレベルの高さに驚かされました。この国は南北に長く、国土の面積や人口は日本に近い。北に位置するハノイは中国国境に近いが、南に位置するホーチミン(旧サイゴン)は亜熱帯で気候も異なる。メコンデルタの肥沃な土壌から生まれる食材は豊富で、魚醤などユニークな発酵調味料から独特の味が生まれる。フランスに統治されていた時期もあり、ベトナム料理はフレンチや中華料理の影響を受け、やさしい味付け。野菜を多く使ったヘルシーな料理として、世界中にファンを持っています。また、通勤・通学途中で屋台のフォーを朝食とする習慣があり、私もしっかりはまりました(笑)。
―日本に帰国し、外資系企業を経て、結婚相手のふるさとでもある福井に行き、ビジネスを始めることになるのですね。
はい、そうです。東京とベトナムでの貴重な経験は、自ら事業をスタートさせるための準備期間という気持ちでした。福井では、最初にベトナムとの特産物の輸出入を始めました。同時期、アジチファーム(現ペントフォークに社名変更)の創業者と出会い、2016年ごろからアジチファームのレストラン、直売所でベトナムのフォーを販売するようになりました。ベトナム時代の人気レストランの経営者から特別にフォーのレシピを教えてもらい、提供したのです。

フォーの麺は、ベトナムで生産されるインディカ米が原料ですが、日本の米と違って長粒米というカテゴリーに属する米で、世界的にはこちらの方が主流です。味覚は日本米のようにしっとりモチモチではなく、パサパサ。当初、乾麺を輸入して提供していたのですが、どうにもベトナムで食べていた美味しい生麺の味にならない。ではベトナム米を輸入すればいいかというと、「日本に米を輸入するとコストが非常に高くなる」という制度の高い壁がありました。そこで、ベトナムで培ったネットワークを利用し、ベトナムの農水省にもサポートしてもらい、栽培用の玄米を輸入して、ベトナム米を生産することにしました。2017年のことです。
福井の田圃で、ベトナム米が収穫できた!
―福井の田圃からベトナム米を無事に収穫することはできましたか?
収穫はできたのですが、国産の製麺機にベトナム米に適したものがありませんでした。そこで、大阪の会社にオリジナルの製麺機を作ってもらうことで、どうにか生麺ができるようになったのですが、この経験がフォーの麺から、米粉の活用へと視点を広げることにつながりました。
―ベトナム米(長粒米)の米粉の用途開発の可能性に気づくことになるのですね。
そうです。例えば、日本の短粒米を使ってパンを作ることは以前から行われているのですが、短粒粉のパンはふんわりとした仕上がり感に関し、小麦粉に比べて評価は低い。ですから、パンといえば小麦がイメージされます。しかし、小麦に長粒米の米粉を混ぜたら、もっちり・しっとりではなく、ふんわり・さっぱり味になる。製品開発の中から、グルテンフリーのパン、シフォンケーキなども生まれました。

―グルテンフリーは現在消費のトレンドになりつつあり、また小麦アレルギーの人には美味しいパンが食べられることは朗報ですよね。
これらの商品は東京と名古屋のデパートでも販売され、人気商品になりました。美味しいもの、優れた商品で、マーケティングさえ上手くいけば、消費者は買い続けてくれることを実感しました。2020年からは大型の加工工場を稼働させ、グルテンフリー認証規格(GFCO)とFSSC2200の認証も取得しました。長粒米粉の用途開発から生まれた新商品には、お米の消費拡大、潜在的なニーズの大きな可能性を感じています。パンは一例であり、長粒米の加工特性を生かした新しい食のニーズ、新商品開発の可能性は大きいと思います。
―長粒米は健康面でも優れていますか?
はい。長粒米の米紛はレジスタントスターチを多く含んでいるのですが、これは糖の吸収を抑制し、腸内の善玉菌の活性化に繋がるという研究開発が行われています。当社でも慶應義塾大学大学院の政策・メディア研究科ヘルスサイエンスラボ代表の渡辺光博教授との共同研究をスタートさせました。
自分で作ってみて長粒米の可能性に気づく
―農業体験がない異業種からの参入は、大変だったのではありませんか?
そうですね。米の生産は初めてで、苗づくりから全て関わることになりました。やってみて分かったことが、長粒米は背が高く茎が太いので倒れにくいので、猪が嫌がる田んぼになる。つまり、鳥獣害の対策がいらないということです。次に、根張りがいいので雑草に強く、その結果、低農薬栽培となります。このような特性は、まさに人手の少ない中山間地向けだったのです。

また、多収米である点も重要です。中山間地の田んぼが大きいところでは長粒米を米粉用米として作りますが、小さな田んぼでは発酵粗飼料としてのWCSを作る。このような工夫をすることで、「農林水産業・地域の活力創造プラン」という農政に上手く適合することができました。主食米から加工用米へという政策のフレームに上手く乗せることができれば、補助金を使って規模を拡大していくこともできます。現在は、このような方針に沿って、福井、石川、滋賀、山形などで米作りをしている勢いのあるプロ農家との連携を推進しています。
―自分でやってみれば、いろいろな可能性に気づくことを御社の事例は教えてくれますね。本日は貴重な話をありがとうございました。
インタビュ−を終えて
日本の農業を守る
少子高齢化の中で日本の人口減少が始まっている。だが、このことが原因で農業における耕作放棄地が増加しているわけではない。農地が消滅している大きな原因は、世界の環境変化の中で、妙にガラパゴス化にこだわった結果であるということだ。
主食米の生産量を減らすことを求められたが、生産する品種を多収量米に変えるのではなく、従来と同じ米を作り、それを米粉にしている農家も多いという。このような中で、これまで農業をやってこなかった企業家が、新しい可能性に挑戦しているのである。
伊藤社長は保守的な農家に向かって、15年後の日本の農業について次のように説明するという。「食料の供給量が需要量を下回るようになると、食糧は生命を維持するために欠かせないので、食料を争って買うことになり、価格が高騰するのは、経済学の原理原則である。平均寿命は伸びても健康寿命がそれほど伸びていない現状では、農業に従事する生産人口は減少し、ロボットなどを通じた生産性の向上は見込めるにしても、今のままでは生産量は減少傾向を維持する可能性が高い。このような環境は、やる気のある農業従事者には間違いなく追い風になる」と。
このストーリーには説得力がある。だが、伊藤社長の話からはもっと明るい日本の農業をイメージさせてもらった。それは、農産物生産の川上から、素材の加工、商品企画、そして最終顧客と直接向き合うことで、作物や素材や商品のストーリーを展開し、それぞれブランド化できるという可能性である。 さらに、素材の組み合わせ次第で、これまでに世界になかった味や香り、食感をもつ商品を開発することで、市場を創造する可能性も見えた。6次産業化というが、能力のある人々がネットワークを構築して目標に向かって手を取り合うこと、そのことが重要である。日本人の味覚は、世界に誇れる。この日本市場でしか生まれない、新しい食品のイノベーションをぜひ目指してもらいたいと思う。
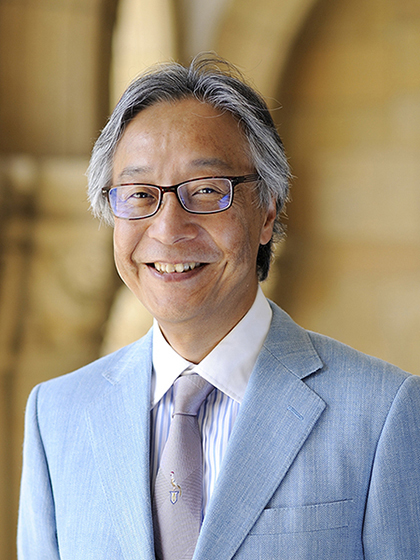
《Interviewer》
古川 一郎
Ichiro Furukawa
武蔵野大学経営学部長/一橋大学名誉教授。
東北大学助教授、大阪大学助教授、カルフォルニア大学ハーススクール客員研究員、一橋大学大学院商学研究科教授を経て現職


