ライフスタイルの変容を生み出すインキュベーター
―トライアルグループの挑戦―
はじめに
「生活のラストワンマイルを支える小売業・流通業が、私たちのライフスタイルを決めている」――トライアルホールディングス代表取締役社長の亀田晃一氏の話を聞きながら、改めてそう思った。
今日の小売業・流通業で、トライアルグループの試みからは目が離せない。それは情報社会である未来の生活者のライフスタイルの変容を見据え、ワクワクする挑戦を続けているからである。
これは、トライアルグループが福岡県宮若市で展開し始めた「リモートワークタウン ムスブ宮若」プロジェクトを取材した所感でもある。結論を先取りすれば、このプロジェクトは、小売業という発想からではなく、「私たち生活者の未来のライフスタイルを育むインキュベーターとなる」ことを目指して構想されたように思われる。

《PROFILE》
亀田 晃一
Koichi Kameda
1964年3月、大分県北海部郡佐賀関町(現在の大分市佐賀関)生まれ。87年3月、横浜国立大学卒業後、富士銀行(現みずほ銀行)入行。調査、プロジェクトファイナンス、ベンチャーキャピタル、企業再生等に携わる。2008年4月、トライアルカンパニー入社。同年6月、同社取締役CFO。10年6月、専務取締役。12年6月、取締役副社長。15年9月、トライアルホールディングス設立、現職。
トライアルグループの新たな挑戦
―トライアルグループは、「株式会社トライアルホールディングス」を中心に、小売店舗を展開する「株式会社トライアルカンパニー」と、AIを中心に新しい技術開発を行う「株式会社Retail AI」などを展開されていますね。
Retail AIでは、来店客が商品をスキャンしてカートに入れると合計金額や関連商品がタブレット端末上に表示される「スマートショッピングカート」を設置し、店舗での欠品や来店客の買い物行動を把握するためのAIカメラ、さらにそれらによって収集されたビッグデータを解析するためのソフトウェアを開発。それをリアルな実店舗で運用しているのがトライアルカンパニーだといえます。社名にふさわしく、このような“トライアル”を続けている原点について、まずお聞かせ下さい。
トライアルグループの創設者でありトライアルホールディングス代表取締役会長の永田久男は創業当時、流通系のソフトウェアなどを開発してきたITエンジニアでした。また、私自身はみずほ銀行出身で、金融業界でキャリアを積みました。
トライアルグループのユニークな活動は、このような多様性を受け入れる企業文化から生まれているのかも知れませんね。

―福岡県宮若市のプロジェクト「リモートワークタウン ムスブ宮若」について、ご紹介をお願いします。
このプロジェクトは、研究開発の拠点から実店舗、宿泊施設、地産地消レストランなど、実に多様な取り組みが大きなシナジーを生み出すように構想されています。「トライアル×福岡県宮若市×九州大学」という、産官学を巻き込み、さらに生産者や取引先と手を結び、リテールDXを巻き起こす一大拠点となることを目指しています。
―なぜ、このような構想を考えたのですか?
未来学者の(ジェレミー・)リフキンは、『限界費用ゼロ社会』において、社会を変えていく原動力はどの時代にあっても「コミュニケーション」「エネルギー」「ロジスティクス」の3つの領域のイノベーションにあると、イギリスの囲い込み運動から始まる欧米の歴史を振り返ることで説明しています。重要なのは、時代の節目節目で、私たちはそれぞれのイノベーションの果実を最大限得るべく、分業と協業の仕組みや社会制度、都市構造を変えてきたということです。
例えば、テレビに代表されるマスメディアの登場や、石炭・石油から電力中心の社会に移行したこと、交通網のインフラが整備され大量物流が可能になったことなどが、現在の東京への一極集中や社会を特徴づけていますし、日本の高度成長がこのことを実証しています。
このように、「コミュニケーション」「エネルギー」「ロジスティクス」のイノベーションを最大限に活用して、社会生活に大きな恩恵がもたらせるように、社会の制度や都市の構造、ライフスタイルまで変容していくとしたら、私たちの生活に最も密着している「小売業が果たすべき新たな役割は何か?」というが問いかけがなされてもいいはずです。トライアルグループが果たすべき本質的な役割は、DXやIoTといった流行の言葉を単に実店舗に実装して押し進めることではありません。「産官学、生産者、取引先と共に未来の生活者のライフスタイルを考えるためのインキュベーターとなる場を構想する」ことではないか。そう考えて、このプロジェクトをスタートさせました。

リアルな現場が持つ、「ヒューリスティック」アプローチの強み
―情報端末の性能向上・小型化とネットワーク化が低コスト化を伴って進行し続けていること。このことが、私たちに直面する変化を引き起こしています。私たちは日常生活でスマートフォンを手放せなくなっていますが、「いまここ」で始まっている大きな変化の本質は、その高性能な端末のCPUにAI readyの領域が実装されてきたことです。AIが社会的に実装されるようになってくる中で、いよいよ大きな変化があるのではないかという期待と不安が渦巻いていますよね。
人々の生活空間における情報空間の大きさは、2000年からわずか20年間で7,000倍以上に膨張したと言われています。もはや、このような膨大なデータを活用するためには、AIが欠かせません。AIがメーカー、小売業者、生活者を含む、社会の隅々にまで普及する中で、それぞれが「どのような関係性を構築し、どのような社会が生まれてくるのか?」が問われています。
このような観点から世界の小売業を見渡せば、どうしてもアメリカのAmazonとウォルマートが目に付きます。特にAmazonは2015年にそれまで小売業No.1だったウォルマートを時価総額で抜き、販売金額でも2021年に逆転しました。Amazonの競争優位の源泉はと言えば、顧客についての圧倒的に大量のデータにあります。データは力なのです。データを情報に変え、小売業が抱えるムダ・ムラ・ムリを効果的に減少させることで生産性を高め、競争優位に立つことができます。「ムスブ宮若」の取り組みは、このような背景から誕生しました。
―情報という点に関して、果たしてAmazonと伍して戦える可能性はあるのでしょうか?
「ムスブ宮若」であり、トライアルカンパニーの最大の強みは、人材を含めてリアルな現場を持っていることにあります。私たちには、大手酒類メーカーと共同で行った事例もあります。
トライアルカンパニーの店舗での消費者の購買行動は、多数のAIカメラを設置することで、リアルタイムで観測し、分析することが可能になりました。分析対象となったのは、棚前行動のデータです。ここでいう棚前行動とは、「顧客が棚の前で立ち止まったのか」「商品を手に取ったのか」「買ったのか、買わないで立ち去ったのか」といった購買行動を指すのですが、これはレジで記録されるPOSデータとは大きく異なります。それは、買わなかった行動や、手に取ってからカートに入れるまでの時間などのデータが、観察される点です。

このデータを分析することで酒売り場のビールの購買行動は、人によって差があることが明らかになりました。分析結果から、ビールの購買量が多く、かつ購入銘柄が決まっている人は滞留時間が短い(約8秒)。それに対して、購入量が少なく多数の銘柄を試す人の滞留時間は長い(約45秒)ということが分かりました。これは、新しい商品を求める顧客ほど売り場に滞留する時間が長い傾向にあることを意味しています。
次に問題となるのは、どのようにしたらこのような情報をビジネスの改善につなげていけるかという点です。この事例では、従来の常識に反しますが、新製品を棚の上の方に、定番商品を人々の目線が集まりやすい「ゴールデンゾーン」に配置する棚割に変えたことで、顧客の利便性を犠牲にすることなく、棚の回転効率を向上させることができました。
―なるほど、普段から顧客を観察している現場の従業員の皆さんの見識がモノをいうのですね。
データサイエンティストでは、顧客の購買行動の特徴を見つけることはできても、具体的にどのようなマーケティング施策が適切かを考えることはできません。そのためには、現場を熟知した人の役割が大きい。すなわち、この事例は「顧客と直に接する現場を持っている」こと、そして「現場を熟知した人々が存在する」こと、さらに「そのような人々が課題に挑戦する」ことの重要さを示しています。新たな工夫を実践して成果を確認する発見的な手法(ヒューリスティックアプローチ)が、有効なのです。
このアプローチの有効性を高めるには、顧客や従業員が、最新システムで実装されたイノベーションを自然に受け入れる工夫(トライアルではレトロフィットと呼んでいる)や実際にやってみるというオペレーションドリブンの企業文化がとても重要になります。

情報社会におけるインキュベーターの姿とは
―ところで、情報社会における小売業の姿は、大量生産・大量販売の時代だった20世紀と同じはずがありません。未来のライフスタイルを育む小売業の姿はどのようなものになるとお考えですか?
トライアルグループでは「リテールDX」と呼んでいますが、この問題の難しさは小売業1社だけでは解決できないことです。問題を解決するために、オープンイノベーションを念頭に置いています。多様な方々に関わってもらうことで、課題解決を図ろうとしているのです。
2017年に業界横断的にAIプロジェクトの実証研究を行う目的で「一般社団法人リテールAI研究会」が設立され、トライアルも当初から参加しています。現在では、メーカーや卸、小売企業など約250社が会員となっている団体です。リテールAI研究会では業界を横断するエコシステムを構築し、データを共同利用することで実証実験を行っています。「ムスブ宮若」プロジェクトにおいても、MUSUBU AIではリノベーションした中学校の同じ建物内に、一般社団法人リテールAI研究会のほか、花王グループカスタマーマーケティング株式会社、サントリー酒類株式会社、株式会社日本アクセス、日本ハム株式会社、P&Gジャパン合同会社、フクシマガリレイ株式会社、菓子メーカー、飲料メーカー、他2社の合計10社と1団体の入居が決定しています。
大量生産・大量販売のビジネスモデルにおいて失われた顧客との対話が、AIの活用によって復活しました。具体的には、店舗内でデジタルサイネージやスマートショッピングカートのディスプレイを通じて、個々人にカスタマイズした情報を提供する技術によって実現しています。

―このインタビュー原稿を書く前に、福岡県糟屋郡新宮町にある貴店で買い物を体験してきました。
新宮でのお買い上げありがとうございます(笑)。これまでの消費者行動の研究によれば、スーパーの買い物の8割は非計画購買(いわゆる衝動買い)というデータがあります。店舗に入る前に決めていないのであれば、店舗内で顧客に積極的に働きかけることで顧客の購買行動を変えることが考えられる。業界を横断した生産者、小売店、顧客がデータを提供し、実証実験を通じてAIの学習が進めば、顧客の行動変容を促し、サプライチェーン全体のムダ・ムラ・ムリを大きく減少させることが期待できるのです。
さらに、大切な日に作る特別な料理についての質問などは、個々の顧客とコールセンターのオペレーターを通じて対話することも可能です。良質で業界をまたがる多くの情報で学習したAIと経験豊かなオペレーターがいれば、買い物コンシェルジュがアテンドするリッチな顧客体験を提供することも可能となり、顧客満足度もきっと大幅に向上させることができるでしょうね。
「スモールマス」への対応が、当面の課題
―百貨店を小売業の王者から引きずり下ろしたのはスーパーマーケットでした。1979年にそれまでの小売業の王者・三越の売上を超えたのは、1957年に創業したダイエーでした。日本人は目の前で魚屋さんが切り身にしてくれるよりも、スーパーマーケットのパック入りの切り身を選んだのです。
バブルの崩壊以降は、特に百貨店の凋落傾向が指摘されるようになりましたが、糸井重里氏の「おいしい生活」というコピーが一世を風靡した1980年代初頭からバブル期にかけては、ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメスなどのプレミアムブランドが多くの日本人の生活の中に入っていきました。わずか半世紀足らずで、私たちのライフスタイルは大きく変容してきているのですね。
コロナ禍の影響は大きく、リモートワークもあっという間に一般的になりました。日常の生活環境はこれからも急速にデジタル社会に組み込まれて行くことでしょう。トライアルの店舗では地域の高齢者の皆さんが、スタッフに聞きながらデジタルを活用した買い物を日常的に楽しんでいらっしゃいます。お客様の置かれた状況をリアルタイムに理解することができれば、もっと正確にコンテクストに応じて対応することができるようになります。
これからは、“スモールマス”の時代です。未来の生活者に対応するためのマーケティング活動は、このようなスモールマスを認識し対応する中から生まれてくると考えています。
―本日は貴重なお話をありがとうございました。
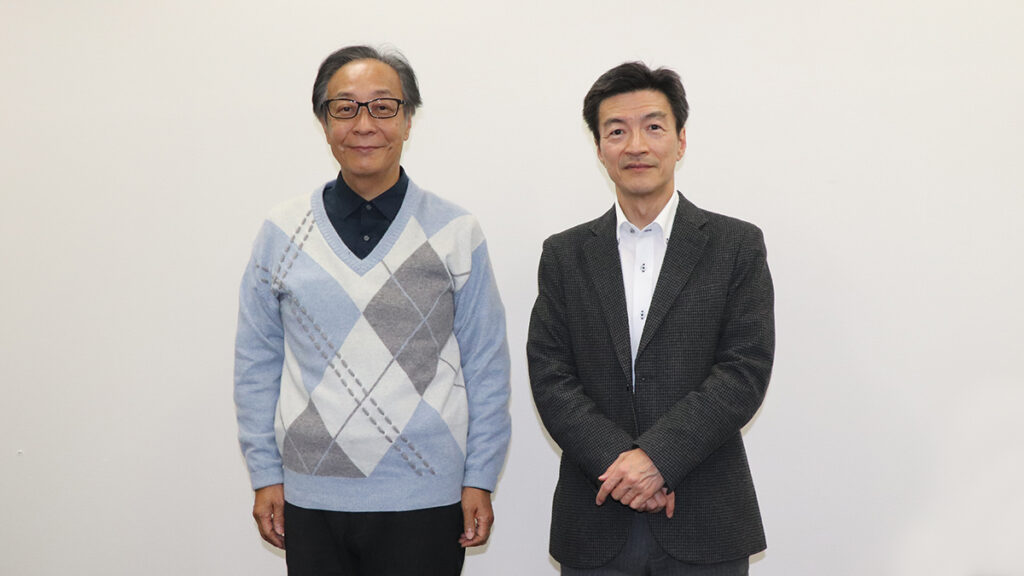
インタビュ−を終えて
「ムスブ宮若」プロジェクトは生活者のライフスタイルの変容を視野に入れ構想されている。プロジェクトには業界横断的で産官学をまたがる多様な人々が参加しているが、それは未来の変化に希望や不安を感じる人が多くいることを証明している。
特に、若者世代においては、年配の世代よりリアルとバーチャルの境界が曖昧になってきている。このような環境変化を意識している人からどのような新しいライフスタイルが生まれてくるのだろうか。この問いに明確に答えることができる人はいないだろう。だから、現場を起点としたヒューリスティック・アプローチが有効なのである。トライアンドエラーがどうしても必要になる。
「ムスブ宮若」プロジェクトは中長期的な時間軸で構想されているが、これからもさまざまな実証実験が行われるに違いない。スモールマスへの多義的な対応を見据えて、マーケティングがどのように変わっていくか。これからも注目していきたい。
参考資料
ムスブ宮若プロジェクト:https://www.youtube.com/watch?v=sPjjBw1y-is&list=TLGGT1YSC0OE2CwxMzEyMjAyMQ&t=48s
永田洋幸、今村修一郎(2021)「AIを小売・流通の現場に実装する方法」Diamond Harvard Business Review
リモートワークタウン ムスブ宮若 プロジェクト、『TRIAL リテールアカデミア』2021年9月号
ジェレミー・リフキン、[訳] 柴田裕之(2015)『限界費用ゼロ社会〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』NHK出版
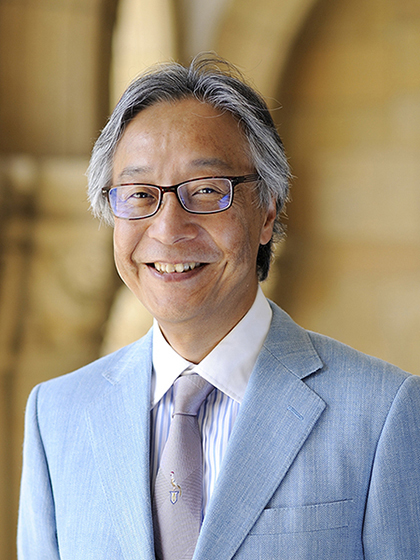
《Interviewer》
古川 一郎
Ichiro Furukawa
武蔵野大学経営学部長/一橋大学名誉教授。
東北大学助教授、大阪大学助教授、カルフォルニア大学ハーススクール客員研究員、一橋大学大学院商学研究科教授を経て現職


